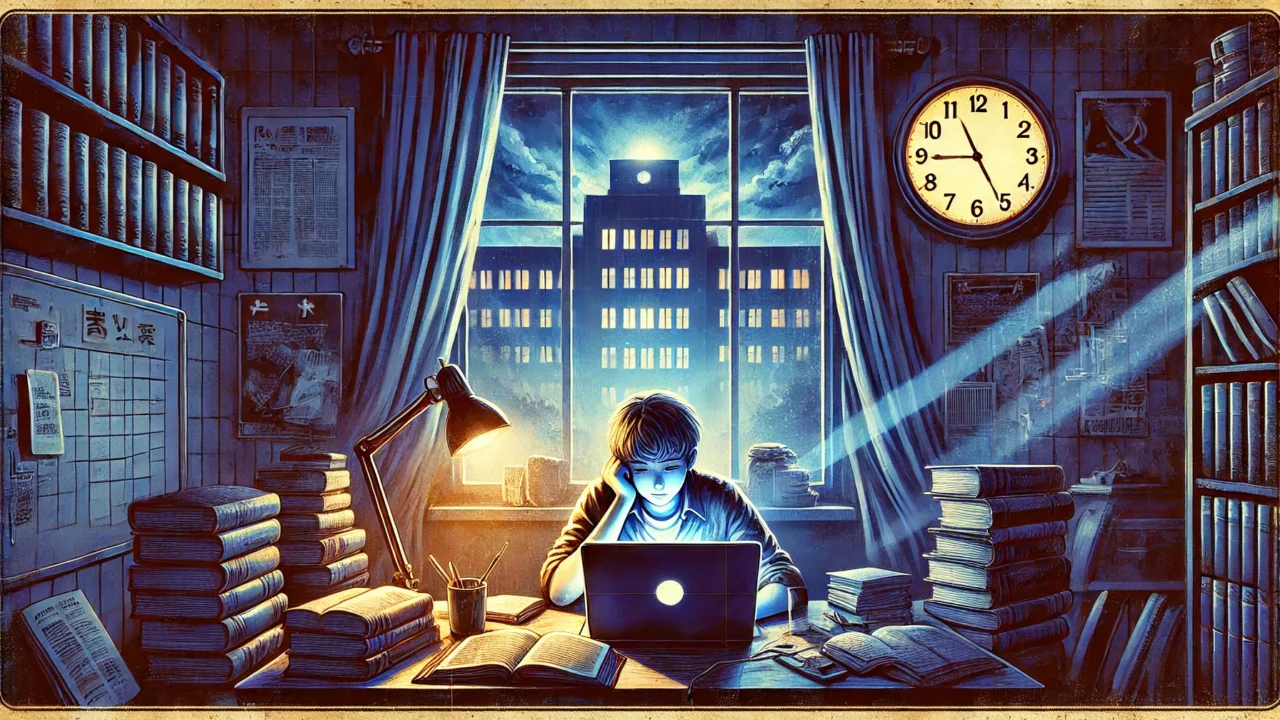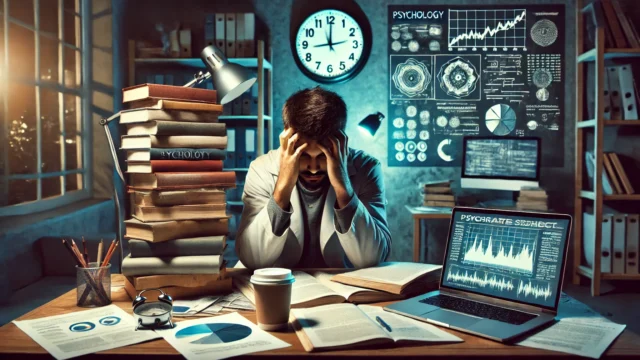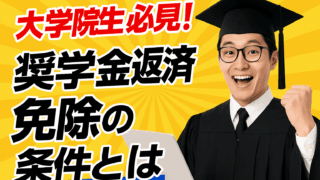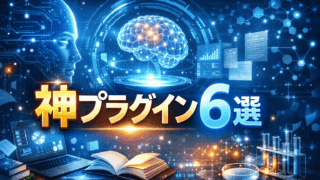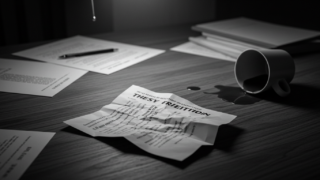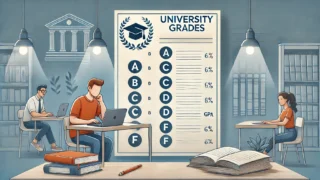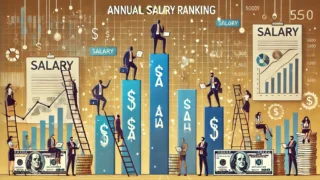「社会人として働きながら大学院に通うのはやっぱりきつい?」
キャリアアップや専門スキルの取得を目指して大学院進学を検討する方にとって、仕事・生活・学業の両立は大きな課題です。
このブログでは、実際に社会人大学院生として過ごした方々が「きつい」と感じた瞬間やその原因を具体的に解説しながら、どのように乗り越えたのかを紹介していきます。
平日の通学、夜間・週末の授業、学費の確保、研究や論文、職場との調整、家庭との時間…想像以上に大変なことも多いですが、工夫次第で乗り越える道はあります。
本記事では、社会人が大学院に通う中で直面する現実的な課題と、自己管理やモチベーション維持の方法、修了までの具体的なステップを詳しくお伝えします。
30代前後でキャリアの転機を迎えた方や、勉強との両立に不安を抱える方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
社会人が大学院は「きつい」?両立が難しい本当の理由とは

社会人として大学院に通うことは、想像以上にきつい現実があります。
仕事や家事に追われる日常の中で、さらに勉強・研究・通学時間まで確保するとなると、心身への負担は決して小さくありません。
特に、時間と体力、そして経済的負担が三大ハードルとして立ちはだかります。本章では、実際に多くの社会人大学院生が経験している課題について、具体的なデータや事例も交えて解説します。
仕事・研究・生活の三重苦:社会人大学院が「地獄」と呼ばれる理由
「フルタイムで働きながら、夜は大学院の講義と課題に追われる生活」。これは多くの社会人大学院生にとって現実です。
例えば、夜間大学院や週末開講の社会人向け課程でも、平日19時〜21時に開講される講義が多く、定時退社できなければ出席もままなりません。また、1週間のうち約10時間以上を授業と課題・予習に割く必要があるケースが一般的で、通勤・残業・家庭とのバランスが難しくなります。
加えて修士課程では2年間で研究計画・中間発表・修士論文をこなさねばならず、これが「地獄」と呼ばれる理由です。中でも理系の研究職志望者は研究室に拘束される時間も長く、土日も研究に追われることが少なくありません。
さらに、学費も大きな壁です。国公立の夜間大学院であっても年間約50〜60万円、私立大学やMBAでは年間100万円〜200万円以上が必要です。加えて教科書代・交通費も加わり、家計への影響は避けられません。
こうした「時間」「体力」「お金」という三重苦に直面するため、精神的に疲弊してしまう方もいます。
【参考】独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 調査報告(2021年)では、社会人大学院生の約43.2%が「生活との両立が非常に困難」と回答しています。
家族や職場との調整が必要な現実とストレス
社会人大学院は、本人の努力だけでは完結しない側面があります。家族の理解と職場の協力が不可欠なのです。
たとえば、小さなお子さんがいる家庭では、夜間授業に出るために保育や夕食の手配が必要です。パートナーの協力が得られなければ継続は困難です。また、家族の協力に心理的なプレッシャーを感じて、途中で断念する方もいます。
職場においても、「大学院に通っている」と伝えることで、人事考課で不利になるのではと感じる方も多く、実際に通っていることを隠している人もいます。
このような状況はストレスの原因となり、モチベーションの維持をさらに難しくします。
また、職場の上司が大学院に否定的であったり、業務量を調整してくれない場合は、通学すら叶わないという声も多く聞かれます。特に中小企業や地方の事業所では、理解のある環境づくりがまだまだ十分とは言えません。
こうした家庭内・職場内の調整は、「勉強の時間」以前に最も大きな壁のひとつとも言えます。
社会人が大学院で「きつい」を乗り越えるための戦略と体験談

「社会人が大学院なんて、自分にできるだろうか…」。
そんな不安を抱えながらも、修了までやり切った人たちはたくさんいます。
この章では、学費のやりくりや時間の使い方、モチベーションの維持方法など、実際の経験者が実践した工夫を紹介します。
これから社会人大学院への進学を考えている方にとって、現実的で再現性の高いヒントとなるはずです。
時間の確保と学費の捻出:両立のための現実的な工夫
時間もお金も限られた中で、大学院進学を目指す社会人には綿密な準備が求められます。
まず、時間の確保について。
多くの社会人大学院生が活用しているのは「朝活」と「スキマ時間」です。
平日朝6時に起床し、出勤前の90分を論文読解や課題に充てる。通勤電車では英語論文を読むか講義録音を再生。
このように、日常の中に学びを組み込む工夫が鍵になります。
また、「ポモドーロ・テクニック」など集中時間を区切って勉強効率を上げる方法も好評です。
次に学費の工面です。
たとえば国公立大学の修士課程は年間約54万円(入学金含まず)、私立では100万~200万円ほどが必要です。
これに対応するため、多くの社会人は教育訓練給付制度(最大112万円給付)や奨学金(JASSOや各大学独自)を活用しています。
また、会社の自己啓発支援制度や、給与天引き型の積立貯金で費用を準備したという事例もあります。
【参考】
・厚生労働省:教育訓練給付制度の概要
・独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
実体験から学ぶ「きつい」瞬間の乗り越え方とアドバイス
ここでは、実際に社会人大学院を修了した人たちの「リアルな声」から見えてきた突破のヒントを紹介します。
●30代・システムエンジニア(男性)
「残業が多い部署だったので、大学院の授業を『毎週火・金の夜に固定』と決め、同僚とシフトを調整しました。
正直、体力的にしんどかったですが、研究テーマが実務に活きたことでモチベーションが続きました。」
●40代・看護師(女性)
「育児と大学院の両立で睡眠時間は毎日4〜5時間。それでも週末に子どもが応援してくれるのが励みになりました。
教授や研究室の仲間の支えも大きかったですね。同期と『励まし合える関係』を作るのも重要だと思います。」
●20代後半・メーカー勤務(男性)
「モチベーション維持には“目的の明確化”がいちばん。
“昇進試験のために論文テーマを通す”という具体的な目標があったことで、迷いなく進めました。」
これらの声から共通して言えるのは、「支えてくれる人の存在」と「自分なりの学びの目的」があれば、たとえ困難でも続けられるということです。
社会人でも大学院に行ける?年齢・期間・進学先のリアルデータ

「社会人でも大学院に行けるのか?」そんな疑問を持つ方は少なくありません。
特に30代~40代で進学を考える方にとっては、年齢や仕事との両立、進学先の選び方、学位取得までにかかる年数といった要素が大きな不安材料になります。
この章では、通いやすさや学費の現実、制度や修了期間のデータをもとに、社会人大学院の実態をわかりやすくご紹介します。
社会人大学院の選び方:通いやすさ・分野・目的別の分類
社会人が大学院を選ぶ際は、「通いやすさ」と「目的の明確さ」が非常に大切です。
まず、夜間・週末開講の大学院は、働きながら通える選択肢としてもっとも一般的です。
たとえば、早稲田大学ビジネススクールや、グロービス経営大学院は、平日夜間や土日に講義を設けており、20代後半〜50代の社会人が多く在籍しています。
また、地方在住者や育児・介護との両立が必要な方にはオンライン対応の大学院も人気です。特に米国MBAなどは、100%オンライン受講+字幕付き講義など、働きながらの学びに特化した設計がされています。
目的別では以下のような分類が可能です:
・キャリア転換:MBA(経営)やMOT(技術経営)
・実務スキル強化:公共政策・教育学・福祉学
・資格取得:臨床心理士・社会福祉士・建築士などの指定科目履修が可能な学部
これらの分野選びは、自分の将来像と現状の仕事や専門スキルのギャップを見つけたうえで決めることが重要です。
大学院の年齢制限・修了年数・キャリアへの影響とは?
社会人が大学院を検討する際に最も気になるのが「今の年齢で通って意味があるか?」という点です。
まず年齢制限ですが、基本的に大学院には年齢制限はありません。
文部科学省の調査によれば、修士課程に在籍する社会人のうち、30代後半~40代前半が最も多いとされています。
修了期間は、基本的に2年間が標準(修士課程)ですが、大学によっては「長期履修制度(最大4年まで在籍可能)」が用意されており、仕事や家庭の都合に合わせた学びが可能です。
博士課程は3年+研究期間が目安とされます。
キャリアへの影響としては、昇進・異動・社内転職への好影響を実感する声が多い一方で、「学位を取ったからといってすぐ転職が有利になるわけではない」という現実もあります。
重要なのは、学位よりも研究テーマや修了後の実践力です。特にMBAや教育系修士などは、職場での成果につなげることで初めてキャリアアップの武器になります。
社会人が大学院で「きつい」を超えた先に得られるものとは

「そこまでして大学院に行く意味はあるのか?」と疑問を感じている方も多いと思います。
たしかに社会人大学院は時間・体力・費用すべてにおいて負荷が大きく、「本当にリターンがあるのか」は重要なテーマです。
この章では、実際に転職や昇進に成功した例や、専門性を高めたことで選ばれる人材になった事例をもとに、社会人大学院の価値を深掘りしていきます。
社会人大学院のメリット:転職・昇進・専門性への影響
社会人大学院の最大の価値は、単なる「学位」ではなく、その後のキャリアの広がりにあります。
例えば、30代後半でMBA(経営学修士)を取得した男性は、在学中に培ったビジネススキルと人脈を活かして、大手企業の管理職ポジションに転職を成功させました。
また、教育系修士課程を修了した女性(40代)は、教員資格とともに専門職採用で市立中学校に採用された事例もあります。
さらに、資格取得が求められる分野――たとえば臨床心理士や建築士など――では、大学院での学習が実務と直結するため、キャリアチェンジの武器として強く機能します。
【参考】
・社会人大学院での転職成功の実例|Postgrad.site
このように、社会人大学院での学びは「昇進試験の通過」や「転職市場での差別化」にも繋がり、結果的に生涯年収の向上に寄与する可能性も高いといえます。
後悔しないために考えるべき「目的」と「覚悟」
一方で、「大学院に行ったけれど何も変わらなかった」と感じる方がいるのも事実です。
その違いを生むのが、進学前の目的設定と、途中でぶつかる壁に向き合う覚悟です。
たとえば、「とりあえずキャリアアップのために」と曖昧な動機で入学すると、途中でモチベーションを失いやすくなります。
一方で、「3年後に専門職として独立するために、〇〇の研究を深める」といった具体的な目標がある人ほど、どれほどきつくても継続できている傾向があります。
また、家庭や仕事との両立に備えて、事前に家族と話し合いを重ねたり、職場と調整して勤務体制の見直しをしたりすることも、成功への布石です。
実際に、こちらの記事では、パートナーとの協力体制を築くことが修了のカギであると紹介されています。
大学院はゴールではなく、スタート地点。目的と覚悟を明確にしておくことで、得られる成果も変わってきます。
社会人大学院のリアルと乗り越えるヒント【まとめ】
社会人が大学院に通うことは、キャリアアップやスキル習得を目的とした有効な選択肢である一方で、「時間・体力・お金」の三重苦によって多くの困難が伴います。特に平日の通学や夜間授業、研究、修士論文などは、仕事や家庭との両立を圧迫し、「地獄のようだ」と表現されることも少なくありません。
さらに、職場の理解が得られなかったり、家族との調整がうまくいかないことで精神的な負荷も大きくなります。
一方で、これらの困難を乗り越えて大学院を修了した社会人は、時間管理やモチベーション維持の工夫(朝活、通勤時間の活用、制度の活用)によって、自分なりのペースで前に進んでいます。また、給付金制度や奨学金、企業の教育支援制度を利用し、費用面の課題もクリアしています。
実体験者たちの声からは、「周囲の支え」「明確な目的」「あらかじめの調整」が、継続と修了の鍵であることが見えてきます。
進学先の選定においては、夜間・週末・オンライン対応など通いやすさを重視し、キャリアの目的に応じてMBA、教育学、臨床心理学などの分野を選ぶのが一般的です。年齢制限はなく、30代後半〜40代の学生も多く在籍しており、修了までの期間は2〜4年が標準です。
そして大学院での学びは、転職・昇進・専門職での採用など、キャリア上の大きなリターンに直結する可能性があります。しかし、曖昧な動機では途中で挫折しやすく、事前に「なぜ学ぶのか」を自分の中で明確にしておくことが成功と後悔を分ける決定的な要因となります。